

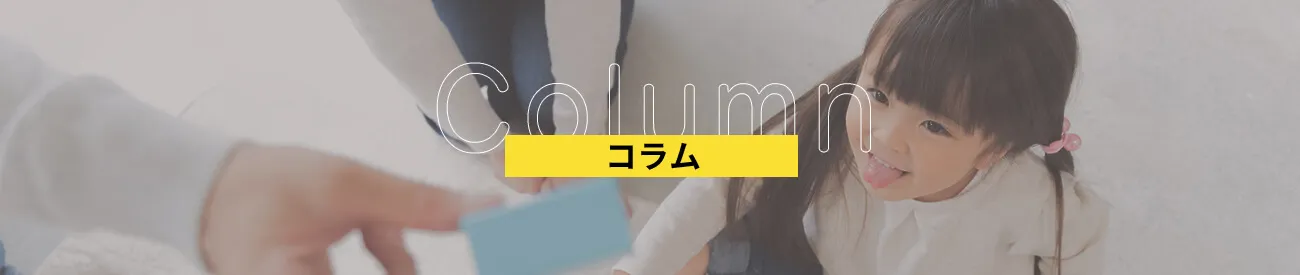

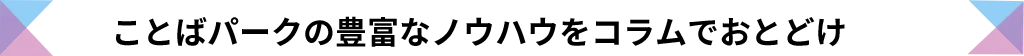
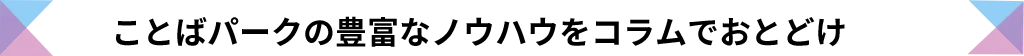
「国語力の高い子」と聞くと、どのようなイメージをされるでしょうか。文を読んでいる姿、図書館で小説を読んでいる姿、学級会で堂々と発表している姿、など人によって持つイメージはさまざまでしょう。
「国語力が必要」と考える方は多いかもしれませんが、具体的にはどのような能力で、どのようにして鍛えていけば良いのでしょうか。
今回はまず「国語力とは何か」について、文部科学省の資料をもとに確認したのち、国語力を高めることが必要である理由、そして国語力を高める方法について解説します。

文部科学省「これからの時代に求められる国語力について」によると、国語力とは以下の2つの領域に分けられます。
① 考える力、感じる力、想像する力、表す力から成る、言語を中心とした情報を処理・操作する領域② 考える力や、表す力などを支え、その基盤となる「国語の知識」や「教養・価値観・感性等」の領域
また、鎌倉女子大学 善本久子氏「学校における国語教育と国語課題」(令和3年12月21日 文化審議会国語分科会国語課題小委員会資料)では、以下のように記載されています。
「求められる国語力の変化」の中の小中高生の国語について
「発達の段階に応じた、語彙の確実な習得、意見と根拠、具体と抽象を押さえて考えるなど情報を正確に理解し適切に表現する力の育成」
このように国語力とは、「各人が知識や経験をもとに、言語を中心とした情報を処理・操作・表現する」という、多くの要素を含んだ総合的能力といえます。

次に、なぜ国語力を伸ばすことが必要とされているかについて考えてみましょう。
たとえば、「考える力」である論理的思考力が弱ければ、算数や数学、理科の問題文から必要な情報を読み取り、その裏にある論理構造を理解することは難しいかもしれません。
また、「表す力」である表現力は、分析力や論理構築力を用いて組み立てた自分の考えや思いなどを、具体的な発言や文章として展開するために必要です。学習においては、自分の考えたことを人に伝え、評価や指摘を受け、改善していくことで、力を伸ばしていくことができます。せっかく考えた内容も、十分に表現し人に伝えることができなければ、そのような成長の機会を逃してしまう可能性があります。
語学など一部の授業を除き、ほぼすべての授業が日本語で行われる以上、このように国語力はすべての科目の学習効率にかかわるといえるでしょう。
文科省の資料には、国語力が求められる場面について次のように解説があります。
「国際化により増加した見知らぬ人や外国人との意思疎通、少子高齢化によって変化しつつある異なる世代との意思疎通、近年急速に増加した情報機器を介しての間接的な意思疎通などにおいて、多様で円滑なコミュニケーションを実現するためには、これまで以上の国語力が求められる」
この例以外でも、国語力が必要となる場はいたるところにあります。友人と話すときには、相手の言葉を受け取り、意図を読み取り、適切に自分の考えを表現する必要があるでしょう。クラブ活動やクラスのイベントで何か企画を立ち上げるときは、過去の資料を読んだり先生から話を聞いたりして、検討し、自分の考えを発表することもあるかもしれません。
国語力が必要となるのは学校の勉強の場だけでなく、日常生活ほぼすべての場といっても過言ではありませんね。
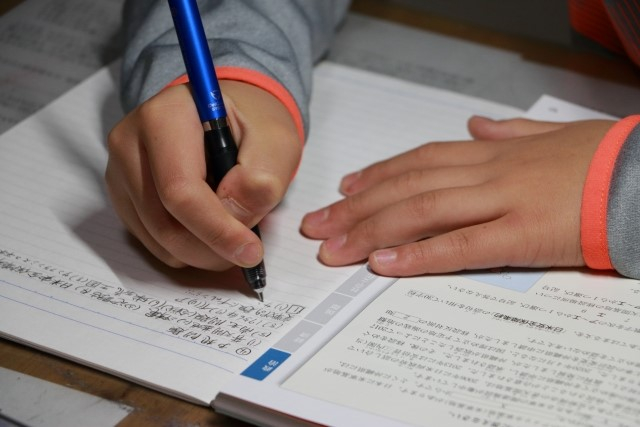
ここからは、国語力 を鍛えるおすすめの方法について解説します。
国語力を鍛えるうえで、読書は有効な手段です。小説や漫画、ニュースやノンフィクション、図鑑など子どもが興味を持ったものからで大丈夫です。
中学受験にかかわる業界などでは「本を読むことが好きだからといって国語ができるわけではない」という声もあります。たしかに国語のテストで点数を取るためには、ただ本を読むことだけでは養えないスキルも必要となるため「本を読めば点数が取れるようになる」わけではないでしょう。
とはいえ、読書が「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」を鍛えながら「国語の知識」「教養・価値観・感性など」すべてにかかわり、バランス良く鍛えていける有効な手段であることには変わりありません。
もし子どもが字を読むのが苦手であれば、読み聞かせをしてあげたり、一緒に音読してあげたりするのも良いですね。接続詞を強調して読む、一息置いて切るところを確認しながら読む、などの工夫で、文の流れを理解するコツを体で覚えていきやすくなります。
読んだり話したりした内容について、いろいろと子どもと話してみましょう。感想でも良いですし、「どんな内容だった?」と簡単に要約してもらうのもおすすめです。
テストで出題されるような質問でも、紙のテストではなく保護者と口頭で行うことで、楽しくストレスなく行うことができるかもしれません。
基本的には子どもの話してくれたことは、内容にかかわらず「なるほど」と受け止めてあげるのがおすすめです。正確性も大切ですが、まずは読んだ内容について考える姿勢を身につけていくことが目的です。「もっと読んでみよう」「読んだことについて話したい」とモチベーションを上げてあげられるような声がけをしていけると良いですね。
読んだ内容について話すときに、多くの表現を使うことを意識してみてください。似たような意味の言葉でも、細かいニュアンスの違いを意識しながら使い分けを身につけていきましょう。
たとえば「やばい」という単語は非常に多くの場面で使われる便利な言葉です。ただ、汎用性が高いことにより、他の言葉を使う機会が減ってしまい、語彙力の低下につながる恐れもあります。
文末を意識してもらうのも大切ですね。たとえば「哺乳類ってなに?」と聞いて子どもが「子どもがお母さんからお乳をもらうやつ」と答えたときは「子どもがお母さんからお乳をもらう動物」と最後の単語を意識するよう促してあげると、表現の正確性が高まっていきます。
ただし、あまり正確な表現を強制し過ぎると、読書やディスカッション自体が嫌いになってしまう恐れもあるので、ほどほどに行うのが良いでしょう。
文部科学省によると、国語の役割は次のように説明されています。
「個人にとっての国語が果たす役割は、「知的活動の基盤」「感性・情緒等の基盤」「コミュニケーション能力の基盤」として、生涯を通じて、個人の自己形成にかかわる点にある」
つまり国語力は、学校の勉強のみならず多くの活動の基盤となり、自己形成のために、そして社会で生きていくために不可欠であるといえるでしょう。
そのような大切な能力だからこそ、適切な方法で、そして急ごしらえになるのではなく、長期の計画のもと着実に身につけていけると良いですね。
ことばパークは講師とのやりとりを通じ、「聞く・話す・読む」力をバランス良く伸ばしていけるオンラインレッスンです。お子さまの国語力を伸ばしたいとお考えの保護者は、ことばパークをぜひご検討ください。
執筆者:杉本啓太
参考サイト:
文部科学省
これからの時代に求められる国語力について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo_kadai/iinkai_47/pdf/93622101_10.pdf
鎌倉女子大学 善本久子
令和3年12月21日 文化審議会国語分科会国語課題小委員会ヒアリング
学校における国語教育と国語課題
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo_kadai/iinkai_47/pdf/93622101_07.pdf
国語力を伸ばすには?大人にも重要な勉強の基礎スキルを子どものうちに高める方法
https://coeteco.jp/articles/12606
小学生の「国語力」を上げるには。3つの方法とオススメ問題集