

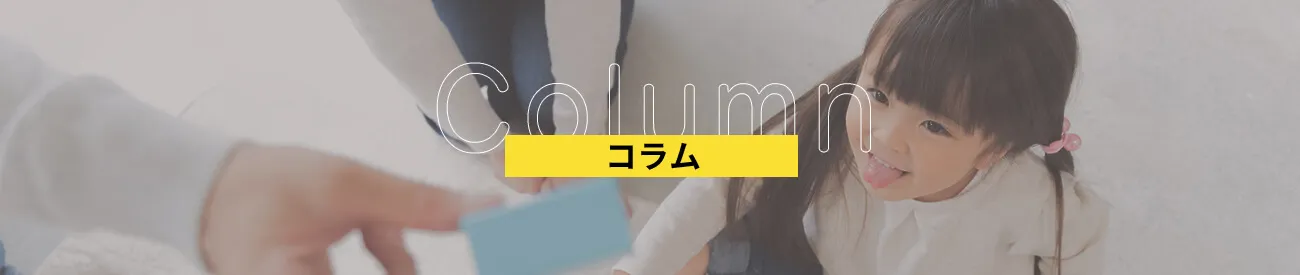

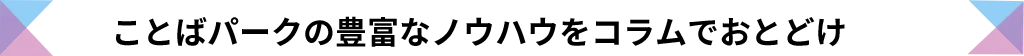
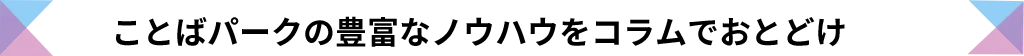
プログラミング教育では、単にパソコンの操作を習得できるだけではなく、論理的思考力や社会・生活へのプログラミング活用における発想力を養うことも可能です。
今回は、プログラミング教育の特徴や必修化、学習内容、メリットなどについて詳しく解説します。

プログラミング教育では、パソコンの活用力やプログラミング的思考を養います。
文部科学省は、プログラミング的思考を次のように定義しています。
「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」
引用:文部科学省「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)」
文部科学省の「新学習指導要領について」によると、2020年度から小学校、2021年から中学校、2022年から高等学校で「プログラミング教育」が必修化されました。小学校におけるプログラミング教育の学習内容や開始する学年は明確に決まっておらず、各自治体や学校の判断で行われます。

小学校のプログラミング教育の学習内容は自治体や学校の判断のもとで決まりますが、文部科学省の資料では例として次の学習内容が明示されています。
・プログラミングを通して、正多角形の意味をもとに正多角形をかく
・身の回りには電気性質や働きを利用した道具があることなどを、プログラミングを通して学習する
・「情報化の進展と生活や社会の変化」を探究課題として学習する
・「まちの魅力と情報技術」を探究課題として学習する
・「情報技術を生かした生産や人の手によるものづくり」を探究課題として学習する
出典:文部科学省「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」

プログラミング教育は、デジタル化が急速に進む現代社会において活躍できる人物を育成するために行われます。文部科学省が提唱するプログラミング教育の狙いについて詳しくみていきましょう。
こどもがコンピューターを活用する機会が増えている一方で、その仕組みを理解している子どもはほとんどいません。以下について気づくことが今後コンピューターを活用するうえで必要とされています。
・コンピューターはプログラムで動いている
・プログラムは人が作成している
・コンピューターには得意なこと、不得意なことがある
・生活におけるさまざまな場面でコンピューターが使われている
小学校のプログラミング教育では、上記について体験を通じて学習できます。なお、コンピューターやネットワークの仕組み、コンピューターを活用した課題の発見・解決の知識・スキルなどについては、中学校や高等学校で学習します。
「身近な問題の発見・解決」や「より良い社会の実現」にコンピューターを活用しようと主体的に取り組む態度を育てる狙いもあります。また、他者と協働でやり抜く態度の育成や著作権などの権利の尊重、セキュリティへの留意といった情報モラルの育成も狙いの1つです。
小学校のプログラミング教育では、本格的なプログラミングの知識や技術は学ばないものの、概念や論理的思考力の習得に向けた学習を行います。ただし、書かれたプログラムはあくまで言語であるため、「聞く・話す・読む力」の基礎能力を身につけておくと、効率的に学習を進めることができます。
しかし、学習のサポート方法がわからない、忙しくて時間を確保できない方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめなのがオンライン学習です。
オンライン学習の「ことばパーク」は、1回25分の短時間レッスンでお子さまの学力(聞く・話す・読む力)を伸ばすことができます。
小学校入学に向けて、お子さまの学力(聞く・話す・読む力)を伸ばしたい方は、ことばパークをぜひチェックしてみてください。