

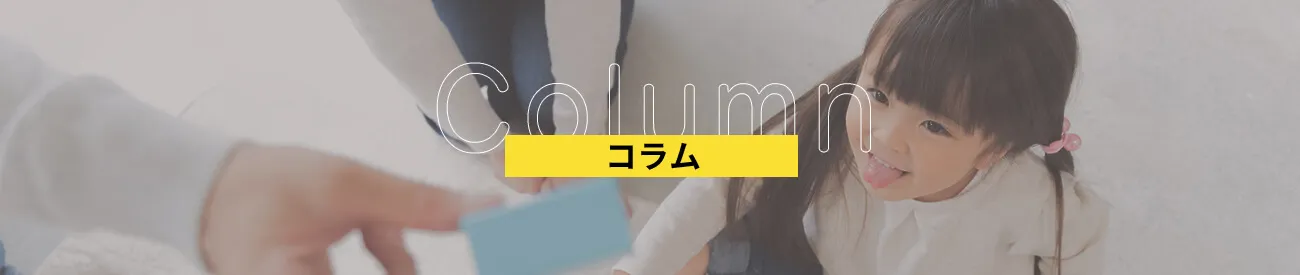

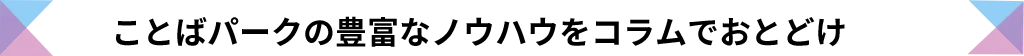
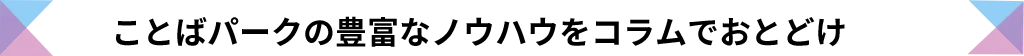
「うちの子は家で勉強しない」とお悩みの方は多いかもしれません。「同じ学年の子はどのくらいの時間、家庭学習をしているのだろう」という声もよく聞きます。
勉強の好き嫌いはお子さんによりますし、どのくらい勉強しなければならないかはそれぞれです。でも勉強するのであれば、なるべくスムーズに、そしてストレスなく臨めるよう成長していってほしいですよね。
今回はまず、小学生の学年別の家庭学習の時間の目安と、家庭学習のポイントについて解説します。そして、家庭での学習習慣をつけるコツを紹介します。

1日当たりの家庭学習時間の目安は、学年×15分といわれています。ここでは、各学年での時間と、時間の使い方の例を紹介します。
低学年のお子さんの場合、家庭学習の時間の目安はだいたい15~30分となります。まだまだ、この時期は長時間の学習は必要ありません。それよりも「勉強する」という習慣づけが大切です。
「おやつを食べたあと、晩ご飯の前に勉強する」「ご飯のあとに勉強をする」などパターンを決めてしまうのがよいでしょう。
「今日は勉強しようかな、どうしようかな」と考えるのではなく、毎日「○○したあとは机に向かう」といったリズムを体に染みつけ、お子さんにとって「当たり前」という認識にしてしまえば、学習に向かうためのストレスが小さくなりますね。
中学年では、家庭学習の時間の目安は1時間弱~1時間くらい。学習する科目も増え、「いつ、何をするか」といった計画も、より大切になってくる時期です。
この時期には、学習することだけでなく「計画する」という工程も、習慣にしてしまうのがおすすめです。家庭学習を始める前に「今日は30分算数を勉強したあと、15分理科のドリルをしよう」といった形で大まかな予定を確認するよう、促してあげてください。
最初はお子さんだけで計画するのは難しいかもしれませんので、「今日はどんな形で進める?」「明日はどうする?」と、保護者の方がお子さんと相談しながら計画するとよいでしょう。
机の前に座ってから「さあ、何をしよう」と考え始めると効率が悪くなりがちです。事前に何をするかを考え、教材を準備しておくようにしてみてください。
高学年になると、家庭学習の時間の目安はだいたい1時間強~1時間半となります。ただし、この頃になるとお子さんによって学習時間は全く異なります。そのため、あくまで目安と考えてください。
お子さんの学習意欲や能力、中学受験をするかしないか、などによって「学習に臨むことのできる時間」「その子にとって必要な学習時間」は大きく変わります。ご家庭で話し合ったうえで、お子さんに合った学習時間やスケジュールを考えるのがよいでしょう。
ただし学習時間が長くなっても、時間の使い方について注意してほしいポイントは、低学年・中学年の子の場合と同じです。「何時から始める」「何時までする」「何を終わらせる」といった点を検討し、習慣にしながら、ストレスなく学習に臨めるように促してあげましょう。学習時間が長くなることで、間に休憩時間などを挟むこともあるかもしれませんが、ダラダラ伸びてしまわないように気をつけたいところですね。

ここからは、家庭学習を習慣化させるコツについて紹介します。
毎回、「どこでやろう」「何時からやろう」と考えると、家庭学習を始めるためのハードルが上がってしまいます。スムーズに家庭学習を始めるためにも、ある程度パターンを決めて、学習に臨めるようにしておきましょう。
日によっては、学校行事があるなど変更が必要な場合もあるでしょう。そのような変更はもちろんOKです。あくまで「この時間にこのように勉強する」という基本パターンを、お子さん自身が身につけられることが大切です。
学習スケジュールは、保護者が作って一方的に渡すのではなく、なるべくお子さん自身が作るようにしましょう。もちろん、一緒に作るのもよいですね。慣れてくれば「お子さんが作って保護者がチェック」といった形もおすすめです。
お子さん自身が主体となって計画を作ることで、「自分で決めたから」と納得し家庭学習に臨みやすくなるでしょう。
また、作ったスケジュールが実際の生活と合わないときは、柔軟に変更していきましょう。「火曜日は体育があって疲れているから、帰ってすぐではなく、晩ご飯のあとに勉強する」などですね。このときも、基本的には「お子さんが考え、決める」という形を取れればよいですね。
せっかく机の前に座っても、いろいろな誘惑が目に映ると集中できません。学習の邪魔になるものはなるべく、学習する場所には置かないようにしたいですね。
具体的には、ゲーム機やパソコン・漫画・テレビなどです。お子さんの部屋にそういった娯楽が多く集中できなさそうであれば、家庭学習はリビングで行うなど、場所を切り替えるのもよい方法です。
学習習慣をつけることで学習のストレスを減らすことが期待できますが、「ゲームをしたいな」「パソコンで動画を見たいな」といったように別の理由でしづらくなってしまっては元も子もありません。お子さんがスムーズに家庭学習に向かえるよう、ご家族で協力して環境を整えてあげましょう。
精選版 日本国語大辞典によると、習慣とは「いつもそうすることが、ある人のきまりになっていること」です。つまり学習習慣とは、学習についての「当たり前の基準」と言い換えられるかもしれません。
人は「当たり前のこと」はスムーズに取り組めますし、そうでないことは「大変だ」と感じる傾向があります。毎日30分の勉強をしている子に、突然「明日から1時間半勉強しよう」と言ったら、とても大変な思いをするでしょう。
何を『当たり前』と感じるか、といった感覚は、お子さんの勉強のしやすさに大きな影響を与えるということです。
決して「家庭学習は長時間の方がよい」というわけではありませんし、どのような「当たり前」を身につけてほしいかはご家庭によって異なります。ご家庭やお子さんの希望を考えつつ、それぞれのご家庭の「理想の学習習慣」を考えられると良いでしょう。そしてそのような学習習慣を身につけられるよう、サポートしてあげてください。
また、以下の記事では家庭学習の習慣化に向けて、学年別・教科別にアドバイスを掲載していますので、参考にしてみてください。
https://kotobapark.889100.com/column/2307_5
ことばパークは講師とのやりとりを通じお子さんの「学びたい」という気持ちを引き出しながら、聞く力・話す力・読む力をバランスよく伸ばしていけるオンラインレッスンです。学習意欲を高め、家庭学習にも積極的にトライしてほしいですね。
お子さまに「楽しみながら学習の習慣をつけてほしい」とお考えでしたら、ことばパークをぜひご検討ください。
執筆者:杉本啓太
参考サイト:
【小学生向け】家庭学習の仕方を解説|コスパ良い教材11社を徹底比較
https://resemom.jp/manabi/elementary-home-study
【小学生の家庭学習】勉強時間目安を学年別に紹介!楽しく習慣化するコツ
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/edu-info/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%AD%A6%E7%BF%92/19996
学力向上の鍵は家庭学習にあり?小学生にオススメの学習方法を解説
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/edu-info/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%AD%A6%E7%BF%92/8688
コトバンク 精選版 日本国語大辞典