

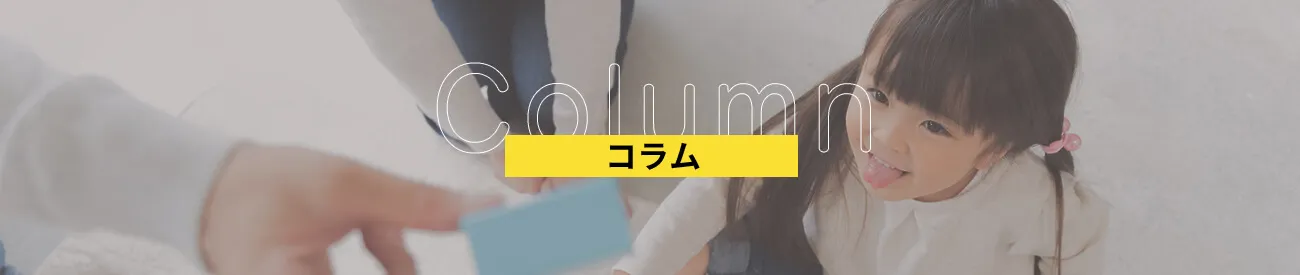

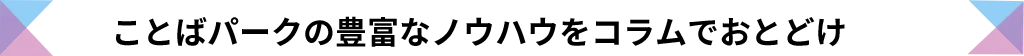
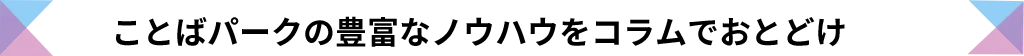
子どもが小学校に入ると、今までとは生活が大きく変化します。その中で、仕事を持っている保護者に立ちはだかるのが「小1の壁」です。小1の壁とはどのようなものなのか、また、壁にぶつかったときどのように対処したらよいのかをご紹介します。

「小1の壁」は、子どもが小学校に入学して環境が大きく変化する中で、仕事を持つ保護者が、子育てと仕事の両立に難しさを感じることをいいます。
保育園では保護者が働いていることが前提となっているため、預かり時間や行事の日程などが配慮されていましたが、小学校ではそのような配慮が得られません。
また、送り迎えをしていたときは、一緒に家を出て一緒に帰ってくることができましたが、それぞれの出発時間や帰宅時間が異なり、子どもが家で一人になる時間が生じてしまうこともあるでしょう。
会社によっては子どもの小学校入学を機に、時短勤務が認められなくなるといったこともあります。相対的に保護者の負担が増え、仕事を続けるのが難しくなるケースもあります。

生活の変化が引き起こす、小1の壁の原因について見ていきましょう。
保育園は朝7時半から預けられるところも多く、基本的に1日8時間子どもを預けることができます。また、最大で11時間まで延長保育を利用することも可能です。しかし、小学校の登校時間は朝8時~8時半ごろ、授業が終わるのは午後2時~3時ごろまでとなり、学校にいる時間は、保育園のころよりずっと短くなります。
保護者が働いている家庭では、多くの場合学童保育を利用しますが、学童保育も保育園に比べると預かり時間は短くなります。
学童保育の開所時間は午後6時ごろまでというところが多く、お迎えの必要もないため、閉所時間になると子どもだけで帰宅しなければなりません。冬の時期は、暗い夜道を子ども一人で歩いて帰る必要があります。
保護者が帰ってくるまで、一人で留守番をさせなければならないようなことも生じます。
小学校に入ると教科書やノートのほかに、副教材や体操着などいろいろな物を持っていくことになります。毎日時間割も変わるため、教材や持ち物を確認する必要もあるでしょう。連絡帳や配布されたプリントを確認して忘れ物はないか、鉛筆はきちんと削れているか、不足している文房具はないかなど、日々のフォローが必要になります。
また、宿題の丸つけや音読のチェックなど、学習に関して手伝うこともあり、保護者の負担は大きくなります。
多く、そのつど休暇をとる必要があります。働いているからといって、PTAの仕事を免除してもらえることは基本的にありません。行事のお手伝いなどもあり、保育園のときと比べると保護者の用事が多くなります。
学童保育に通っている場合は、夏休みや冬休み、春休みは学童で預かってもらえますが、毎日お弁当を作る必要があります。忙しい保護者にとって、長期休暇の間、毎日お弁当を作るのは大きな負担になるでしょう。
時短勤務を認めている会社でも、子どもが小学校に入学したタイミングでフルタイム勤務に戻すよう言われることも多いものです。
学童の終わる時間までに子どもを迎えに行けない、子ども一人で留守番をしなければならないといったことが起こります。

小1の壁を乗り越えるには、どうしたらよいのでしょうか。具体的な対処方法をご紹介していきましょう。
民間の学童保育やシッターサービスなどを利用するのも一つの方法です。民間の学童は、預かり時間が長いため、保護者の帰宅時間に合わせて利用することができます。また、学童が終わって保護者が帰ってくるまでの間、シッターサービスを頼んでもよいでしょう。
民間サービスは費用が比較的高くなるため、ピンポイントで使うなどの工夫をしながら、うまく活用していくとよいでしょう。
自治体によっては「ファミリーサポート」などの、子育て支援のサービスを行っているところもあります。事前の申し込みや顔合わせなどが必要ですが、民間サービスよりは安く利用することができます。
子どもの小学校入学を機に、働き方を見直すのも考え方の一つです。急な対応が必要になる仕事や残業の多い仕事をこのまま続けてよいのか、子育ての間だけ仕事を減らせないかなど、検討してみてもよいでしょう。
会社に事情を話して相談してみるのも一つの方法です。会社によっては時短勤務や配置換えを検討してくれることもあるはずです。また、フレックスタイムやリモートワークの活用などができないか、勤務形態について相談してみましょう。
保護者同士で情報交換をして、協力し合うという方法もあります。帰りが遅くなりそうなときには迎えを頼み、その代わり休日には子どもを預かるなど、どちらか一方に負担がかからないよう話し合いながら協力してみてはいかがでしょうか。
学童が終わってから習い事をさせるのも一つの方法です。学童の閉所時間には間に合わなくても、習い事の終わる時間には迎えに行けることもあるでしょう。
共働き家庭が増え、小1の壁に悩む家庭は増えてきています。まずは、家族や夫婦の間でよく話し合い、誰か一人に負担がかからないよう調整することが大切です。
さまざまな民間サービスも登場してきているので、頼れるものには頼るという精神でうまく乗り切っていくとよいでしょう。
忙しい毎日の中、学習フォローが難しいという場合は、お子さまの帰宅後の習い事として、オンライン学習「ことばパーク」をぜひご利用ください。
執筆者:五十嵐麻弥子
参考資料
1) 「『小1の壁』が発生する原因とは?入学前の対策と入学後の対応を解説!」コエテコ.
https://coeteco.jp/articles/12291
2) 「小1の壁はなぜ起こる?原因から6つの対策まで」ウィズダムアカデミー.
https://wisdom-academy.com/news/column/elementary_school_wall
3) 「小1の壁とは?原因や問題点、乗り越える方法を具体例とあわせて紹介」SDGsAction.
https://www.asahi.com/sdgs/article/14811297
4) 「「小1の壁」ってどういうこと?原因と対策を徹底解説! 【FP監修】」KIDSLINE.