

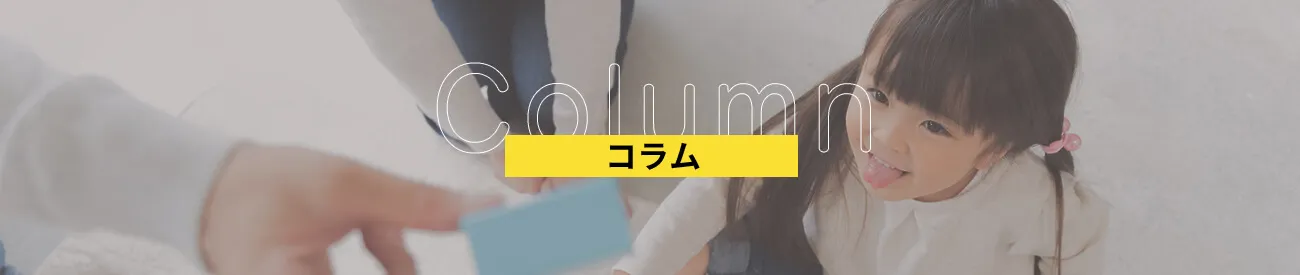

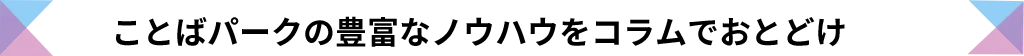
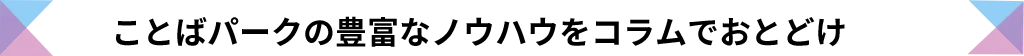
いつも子どもが何かしら忘れ物をする、何度言っても忘れてしまう……そんな悩みを抱える保護者は多いのではないでしょうか。子どもだから仕方ないとは思っても、あまりに忘れ物が多いと心配になってしまいます。子どもの忘れ物の原因と、その対処方法についてご紹介していきましょう。
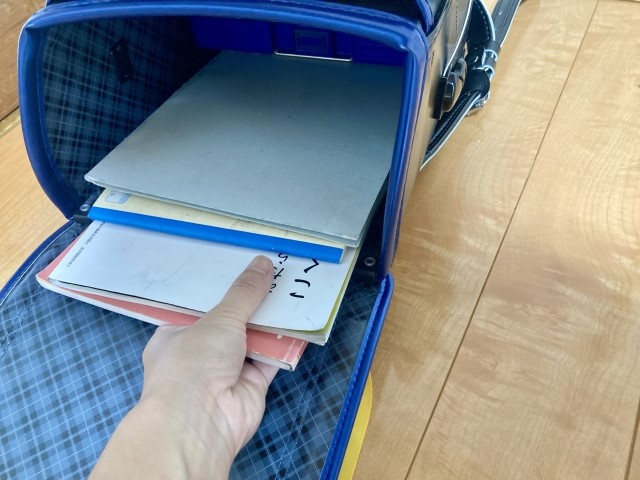
子どもに限らず、大人でもうっかり忘れ物をしてしまうことはあるものです。ただ、子どもの忘れ物があまりに度重なると、イライラしたり心配になったりすることもあるでしょう。
なぜ子どもは忘れ物をしてしまうのか、その理由について見ていきましょう。
学校へ持っていくものを忘れないためには事前の準備が必要ですが、家に帰ってきた安心感から、準備を忘れてしまうことがあります。
家に帰るとホッとして、自分の好きなことに時間を使いたくなるものです。リラックスしてゲームをしたりマンガを読んだりしているうちに、翌日の準備を忘れてしまうのです。
時間的な余裕がないせいで、忘れ物をしてしまうこともよくあります。
学校から帰ってきたあと、友達との約束や習い事などで出かけなければならないと、気持ちが焦ってしまうものです。また、保護者の帰りが遅い場合は、限られた時間の中でいろいろなことをしなければならないため、気持ちに余裕がなくなります。
夜更かしをして朝起きるのがギリギリになり、準備をする時間がなくなって、忘れ物をしてしまうこともあるでしょう。
小学生は毎日たくさんの持ち物を持って登校しています。教科書やノート、文房具をはじめ、体操着、給食着、絵の具・書道・工作の道具、特別活動で使うものなど、実にさまざまな持ち物があります。
時間割に合わせて毎日違う持ち物を忘れずに準備するのは、大人が思う以上に負担のかかるものといえるでしょう。
何事も後回しにする性格の子どもは、忘れ物をしやすいといえます。準備をしなければいけないことはわかっているものの、今やるのは面倒くさい、あとでやればよいと考えて後回しにしているうちに、準備を忘れてしまいます。
もらったプリントがぐちゃぐちゃになっている、帰ってきたらランドセルをその辺に放り投げておくといった性格の子どもも要注意です。整理整頓がうまくできないと、何がどこにあるのかわからなくなるため、忘れ物をしやすくなります。
子どもによっては、持ち物やしなければならないことの重要度が十分に理解できていないこともあります。大切なことだと感じていないため、忘れてしまうというケースです。
また、先生の話を聞き逃したり、プリントを失くしたりしてしまい困ることもあります。子どもの発達段階や特性によって、忘れ物が多くなることもあります。

子どもが忘れ物をしないためには、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。
朝になってあわてて準備をすると、忘れ物をしやすくなります。翌日の準備は前日に済ませることが大切です。低学年のうちからその習慣をつけさせることは、忘れ物を防ぐうえで大きな効果があります。
すでに高学年になっているという場合は、前日に準備をすると忘れ物を大幅に減らせることや、落ち着いて準備をすることで抜け落ちがなくなることなど、そのメリットを言葉で説明して理解させていきましょう。
学校から帰ってきてすぐに翌日の準備をするなど、「準備する時間」を決めてしまうのがおすすめです。帰ってすぐ用事で出かけなければならないときは、用事から帰ってすぐ、夕食前、夕食後、お風呂に入る前、寝る前などに準備をさせてみてはいかがでしょうか。
ポイントは時間を決めるということです。習慣がつくことで、時間になると「準備をしなければ」と思えるようになっていきます。
ものを整理する習慣が身につくと、忘れ物は少なくなっていきます。どこに何があるのかがわかると探す手間がなくなり、すぐ準備することができるようになるからです。
いきなり細々したことを決めると子どもは面倒になってしまうので、学校で使うものを1か所にまとめておくことから始めてみましょう。
また、帰ってきたら、いったんランドセルの中身を出して、プリントの出し忘れがないか確認することも大切です。
取り組まなければならないことが多いと、大人でも頭がパンクしてしまうものです。習い事や塾など学校外の活動が忙し過ぎないか、見直してみることも大切です。
子どものうちにいろいろなことを経験させたいという気持ちもわかりますが、課題を減らすことで気持ちに余裕が生まれ、忘れ物が減るということもあるでしょう。
普段から子どもとコミュニケーションがうまくとれていると、学校で必要なものがわかってくるものです。学校での様子や今日習ったことなど、こまめに話ができる雰囲気作りをしておくことも大切です。

忘れ物をなくしていくためにできる、具体的な対策の例をご紹介します。
今日学校ではどのような授業があったのか、クラスでどのようなことが起こったのかなど、学校の話題を出すのがおすすめです。話をしているうちに、子どもが翌日の予定や持ち物のことを思い出す可能性があるからです。
食事の支度や、片付けをしながらの短い時間でもかまいません。子どもの学校での様子もわかり、一石二鳥といえるでしょう。
教科書、ノート、文房具など、いつも使うものをリストにして、チェックしていくのもよい方法です。月曜日には体操着、上履き、給食着など必ず持っていくものがあるはずです。準備ができたらチェックを入れるのを習慣にします。
忘れてはいけないものを付箋に書いてランドセルや子ども部屋のドアに貼ったり、ホワイトボードに書いたりして、家族の目に入るようにしておくのもよいでしょう。
子どもが忘れてしまっても、家族が気づいてフォローすることができます。
スマートフォンやタブレット端末に入っているリマインダーアプリを使い、持ち物や予定をリマインドするという方法もあります。
さまざまな理由で子どもは忘れ物をしてしまいますが、少し工夫をすることで改善することが可能です。
初めのうちは、保護者が一緒に準備をするなどのサポートが必要かもしれませんが、慣れてくれば一人でできるようになるでしょう。
子どもによっては、忘れ物が多いこととワーキングメモリが関係していることもあるものです。そのような場合は、ワーキングメモリを鍛えることで、忘れ物が減っていく可能性があります。
ことばパークでは、ワーキングメモリを鍛えて学力アップを図っています。お子さまの忘れ物が気になるときは、ことばパークの活用をぜひご検討ください。
執筆者:五十嵐麻弥子
参考資料
1) 「なんで直らない?忘れ物を繰り返す子どもの原因と対策を調べました!」はみっく通信.
https://hamic.ai/blogs/hamiccommunication/wasuremono
2) 「忘れ物が多い子、時間に遅れがちな子、対策は?」きずなネット.
https://coelog.chuden.jp/child-rearing/something-forgotten-countermeasure
3) 「忘れ物が多い原因は発達障害? よくある4大特徴と今すぐできる5つの対策【心理カウンセラー監修】」マイナビ子育て.
https://woman.mynavi.jp/kosodate/articles/23560
4) 「子どもの忘れ物、防止するコツとやってはいけないこととは?」ベネッセ教育情報.