

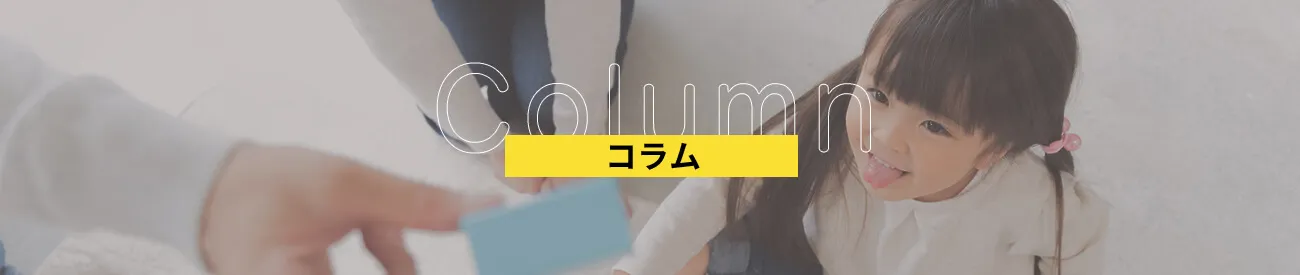

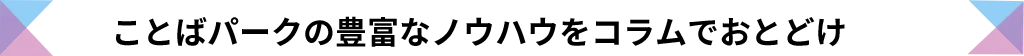
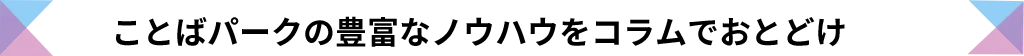
夏を前に毎年必ずやってくる「梅雨」。天気予報で「梅雨入り」などという言葉を聞いて、「梅雨って何だろう?」という疑問を抱く子どももいるでしょう。外出できない雨の日には、梅雨の意味や由来について、子どもとゆっくり話してみてはいかがでしょうか。

梅雨は毎年5月下旬から7月上旬ごろにかけて続く、雨の季節のことをいいます。朝鮮半島や台湾、中国の一部など、東アジア地域に見られる気候ですが、日本の梅雨は特に期間が長いのが特徴とされています。
1ヵ月以上にわたって雨やくもりの日が続き、1日中雨が降り続く日もあります。湿度が高くジメジメして蒸し暑いのが特徴です。ただし、ときに「梅雨寒」といって、季節外れの寒さが襲うこともあります。

梅雨は「梅の雨」と書きますが、その由来はどこにあるのでしょうか。梅雨の表記については諸説ありますが、そのうちの3つをご紹介しましょう。
梅雨は、中国からやって来た言葉といわれています。中国の揚子江流域では、3月ごろに梅の花が咲き、6月ごろその実が熟します。「梅の実が熟すころの雨」ということで梅雨と呼ばれるようになり、それが日本に伝わったという説があります。
梅雨の時期には雨が続いて湿度が高まり、カビが生えやすくなります。そのためもともと「カビ(黴)の季節の雨」という意味で「黴雨」と表記されていたといいます。これに同じ「ばい」という読み方をする「梅」の字があてられて「梅雨」になったという説です。カビの雨では印象が悪いので、梅の雨に替えたという話もあるそうです。
3つ目は、梅という字にはあまり意味がないという説です。
この季節は毎日雨が降るため、毎日の「毎」が入っている「梅」という漢字を使って梅雨にしたということです。また、通常の倍の量の雨が降るという語呂合わせで、倍と同じ音の梅をあてて梅雨としたという話もあります。

梅雨は「ばいう」とも読みますが、一般的には「つゆ」という言い方をします。その語源についてもご紹介しましょう。
植物や木の葉などが雨に濡れると水滴になり、露がしたたり落ちてきます。露の様子からそのまま梅雨に「つゆ」という言葉をあてはめたという説です。
また、「露に濡れて湿っぽい」という意味で、和歌や俳句の季語として使われている「露けし」という言葉が転じたともいわれています。
梅雨の時期に熟す梅の実が、熟し過ぎて潰れてしまった様子を「潰える」と表現したことが、語源になっているという説もあります。潰えるを「潰いゆ」と言っているうちに、「つゆ」になったということです。
長雨が続くと食べ物にカビが生えてしまい、ダメになってしまうことがあります。カビが生えて食べられなくなる様子を「費える」といい、それが転じて「つゆ」になったという説です。

そもそも梅雨にたくさん雨が降るのはどうしてなのでしょうか。
5月下旬~7月上旬にかけて南東からは温かく湿った風が、また、北東からは冷たい風がやってきます。温かい風は太平洋高気圧、冷たい風はオホーツク海高気圧といいます。この二つの高気圧が、日本の上空でぶつかり合うと気圧の境目に梅雨前線ができます。二つの高気圧が同じくらいの強さで押し合うので、1ヵ月以上にわたって梅雨前線が日本の上にとどまり続け、多くの雨を降らせるのです。
温かい空気は軽いため、冷たい空気とぶつかるとどんどん上昇していきます。空気は上空に上がると冷やされて雲になり、それが雨となって地上に降ってきます。梅雨に多くの雨が降るのはそのためです。
温かい空気(暖気)と冷たい空気(寒気)がぶつかり合うと前線ができます。いずれ、暖気・寒気のどちらかが強くなり、前線の位置が移動します。
太平洋高気圧とオホーツク海高気圧の場合、オホーツク海高気圧の方が強く、梅雨前線が北海道まで北上しないことが多いという特徴があります。そのため、北海道には梅雨がないとされているのです。
雨が続くとなかなか外で体を動かせず、子どもも退屈してしまいます。また、保護者も子どもとどのように家で過ごしたらよいか、悩んでしまうことがあるかもしれません。ただ、雨で家にいることは、子どもとたくさんおしゃべりをするよい機会ともなります。
梅雨はデメリットだけではなく、農作物の成長を助けたり、夏の水不足を防いだりするメリットもあります。梅雨の語源や梅雨が起こるしくみを家族で話し合い、長雨の時期を楽しく過ごせるとよいでしょう。
執筆者:フリーライター/不登校支援カウンセラー 五十嵐麻弥子
参考資料
1) 「【梅雨とは?】意味や由来を子どもに分かりやすく説明しよう」保育求人ラボ.
https://hoiku-labo.com/news_312.html
2) 「「梅雨」に「梅」が使われているのはなぜ?意外と知らない語源を学ぼう!」ママソレ.
https://mama.chintaistyle.jp/article/why_rainy-season_plum
3) 「【梅雨】の意味とは? 言葉の由来や成り立ち・梅雨の役割を解説」Domani.
https://domani.shogakukan.co.jp/526027
4) 「「梅雨」の語源は?読み方・名前の由来と豆知識をご紹介!」美的生活.
https://biteki-seikatu.com/life-style/rainy-season-etymology
5) 「梅雨の意味・由来・語源を子供向けに説明するには?」歴史・由来・意味の雑学