

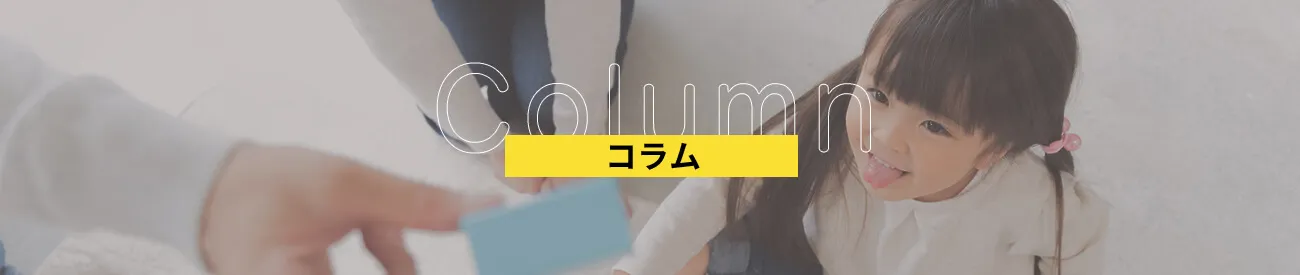

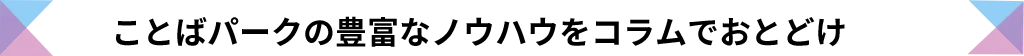
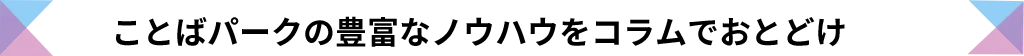
「うちの子はことばが遅いのでは?」と、気になっている保護者は意外と多いものです。検査をしたり早目に対処したりする必要があるのか、悩んでいるという人もいるのではないでしょうか。ことばの発達に差がある理由と、発達をうながす働きかけについてまとめます。

子どもはどのようにしてことばを獲得していくのでしょうか。順を追って見ていきましょう。
子どもがことばを話せるようになるには、まず心身の発育が必要です。視覚・聴覚・触覚といった感覚器官の発達が土台となり、脳や神経が発達していきます。運動機能や情緒が育っていく中で、少しずつことばの理解も進んでいきます。
ことばが発達していくには、いくつかの力を順番に獲得していくことが大切です。
まずは、語彙力です。単語の意味を理解することで、使えることばが増えていきます。次に、一つ一つの音を順番に並べて単語を作る力、それを並べて意味の通る内容に組み立てる力が必要です。最後に、自分の伝えたいことを伝えたり、相手の言いたいことを理解したりする相互のコミュニケーション能力が身につくことで、ことばをスムーズに話せるようになります。それぞれの力を獲得する時期は、子どもによって異なります。年齢にこだわらず、今子どもがどの段階にいるのかを見ることが大切です。
子どもによって、発達のスピードは大きく異なります。また、一つの段階に長い時間がかかっても、次の段階はあっという間に通り過ぎてしまうということもあるでしょう。特にことばの発達にはさまざまな要素が関連しているため、長い準備期間が必要です。足踏みをしているように見えても、子どもの中ではさまざまな力が育っています。あまり焦らず、おおらかに見守ることも大切です。

発達に個人差があるとはいえ、子どものことばが遅れているかもしれないと心配になるものです。ことばの遅れには複雑な要因がからんでいるため、どれか一つに特定しづらいものですが、要因として考えられていることをご紹介します。
前述の通り、子どもの発達には大きな個人差があり、全体的な発達がゆっくりしている子どももいます。ことばがなかなか出てこないのは、まだその発達段階に達していないということも考えられます。また、一つ一つの力はついてきているものの、その連携が十分ではないということもあるでしょう。いずれの場合も、子どもの発達を待つ必要があります。
家族の人数が少ない、話しかけられる機会が少ないことなども、ことばの遅れに関わるといわれています。ことば自体を聞く機会が少ないと、なかなか語彙が増えていかないでしょう。また、周囲の人からの愛情を感じられず情緒の発達が不十分となり、ことばの発達に影響が現れることもあります。
家庭内での暴力や暴言など、恐怖を感じるような環境で育っていることも、ことばの発達に関わるとされています。強いストレスは、ことばの土台となる子どもの心身の発達に影響して、発育を妨げる可能性もあるといわれています。
耳の聞こえがよくないことが、ことばの遅れにつながることもあります。生まれたときから聴覚障害がある場合と、中耳炎など耳の病気やおたふく風邪などをきっかけに聞こえにくくなる場合があります。成長途中で聞こえづらくなったときには、周囲も気づきにくいため注意が必要です。
また、発声に関わる口や唇の形、のどの状態など、生まれつきの身体的な問題が影響するケースもあります。
コミュニケーションの取りにくさが特徴的な自閉スペクトラム症などの発達障害が、ことばの遅れと関わることもあります。かんしゃくを起こしやすい、こだわりが強い、視線が合いにくいといった症状が見られます。

子どものことばが遅いと感じたとき、発達をうながすにはどのような方法があるのでしょうか。
ことばが出てくる前段階として、愛情を伝えながら情緒を育てていくことはとても重要です。子どもと目を合わせながらたくさん話しかけ、コミュニケーションを深めましょう。
肌と肌との触れ合いは、気持ちを安定させる効果があることが知られています。折々スキンシップをとり、子どもの情緒を安定させてあげるとよいでしょう。発達障害の子どもの中には肌に触れられるのを嫌がる子もいるので、子どもが安心できるような形で見守ることを心がけます。
子どもに話しかけるときは、ゆっくりはっきりした発音で話しかけることを心がけます。早口で話しかけると、うまくことばを聞きとることができず、ことばの意味も理解しづらくなってしまいます。また、難しいことばや複雑な内容も避けた方がよいでしょう。ゆっくりはっきり端的に話すことで、子どもの語彙力は増えていきます。
子どもが遊びを楽しんでいたり何かに集中したりしているときは、子どものペースを大切にしてあげましょう。大人の都合で一方的に切り上げさせたり、「早く早く」とせかしたりするのもよくありません。子どものペースに合わせることで、自発的な発達がうながされます。
体を動かすと脳が活性化して、発語にもよい影響があるといわれています。その意味で、積極的に外遊びをするのはおすすめです。また、子どもといっしょに散歩をしながら、目に入るものをことばにして教えてあげるのもよいでしょう。
ことばの発達は個人差が大きいので、あまり神経質にならないことも大切です。どうしても気になるときは、医療機関や保健センターで相談をしてみるとよいでしょう。医療や福祉の対応が、ことばの発育をうながすきっかけになることもあります。
ことばパークでは、お子さまが楽しくことばを増やしていけるような働きかけをしながら、国語力を伸ばしていきます。お子さまの国語力アップをお考えの際は、ことばパークをご活用ください。
執筆者:フリーライター/不登校支援カウンセラー 五十嵐麻弥子
参考資料
1) 「子どもの「ことば」の発達とは?「ことば」の遅れの要因と発達を促す5つのポイント」PARK.
https://parc.medi-care.co.jp/blog/121
2) 「言語聴覚士・寺田奈々先生に聞く【子どものことばの発達】遅れ、吃音に悩んでいる親御さんは相談を」HugKum.
3) 「いつから話す?0~4歳児の「言葉・発語」の発達段階、男女差や個人差について」コノバス.
https://conobas.net/blog/education/11173/
4) 「言葉の発達の遅れ、どうすればいい?:原因と対応」NOVAKID.
https://www.novakid.jp/blog/kotobanookure-sono-genin-to-taio/
5) 「言葉の遅れ(言語発達遅滞)が心配|原因や必要な療育についても紹介」子ども運動教室LUMO.